先頃IED社から出版された『第五次辺境戦争』(GDW / HJ / IED)は、往年のSF TRPG『TRAVELLER』(GDW)の世界を舞台にした星間戦争を扱ったシミュレーションゲームです。
舞台となる「スピンワード・マーチ星域」は、<ソロマニ人(地球人)>が樹立した「銀河帝国」と、「ゾダニ評議国」「ソードワールズ連合」「ヴァルグル連合」といった異星人の複数の星間国家の勢力圏が緩衝宙域や非武装宙域を挟んで接した紛争地帯です。
タイトルの「第五次辺境戦争」は、「ゾダニ」「ソードワールド」「ヴァルグル」の3勢力が反銀河帝国の旗の元に結集して引き起こしました。不意を突かれた銀河帝国は次々と拠点を失うのですが帝国内の他星域から増援を得ることで反攻を開始するというのが大まかな展開となります。
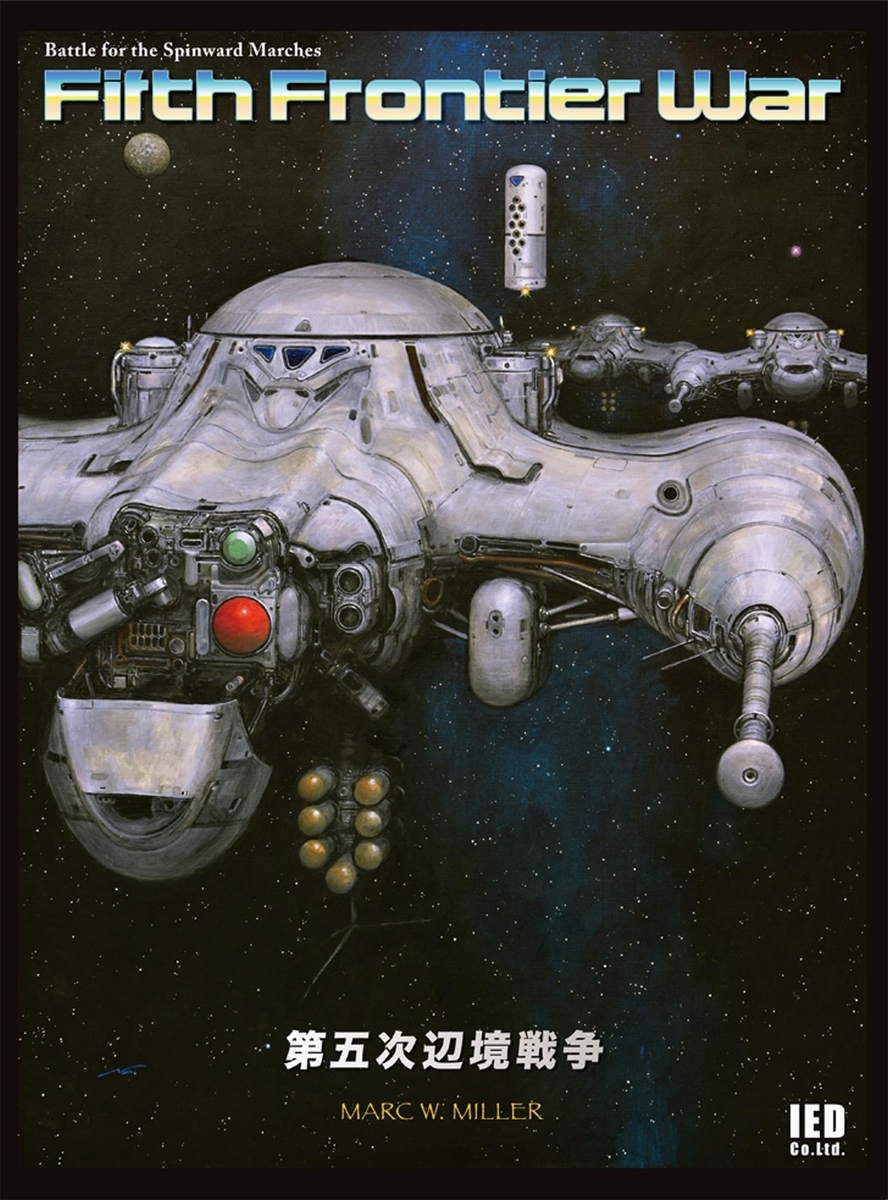
往年のSFテーマのTRPG「トラベラー」世界を舞台にし、先頃再版されたウォーシミュレーション「第五次辺境戦争(Fifth Frontier War)」(GDW/IED)を対戦。 40年ぶりのトラベラー世界は懐かしく、変わらず魅力いっぱいで終始ワクワク感 (続く)#ウォーゲーム #ボードゲーム #Wargames #Traveller#GDW #IED pic.twitter.com/0NeGVMLtwD
— yuishikani (@yuishikani1) 2024年11月30日
「スピンワード・マーチ星域」は、本家にあたるTRPGの公式シナリオ集で、頻繁に舞台とされた星域のため、星域図(本ゲームのマップ)を見ただけでも、かつて冒険した懐かしい地名ならぬ星系が並んでいます。本ゲームが舞台とする世界の技術・軍事・地政学・歴史といった背景要素は『TRAVELLER』に依っているため、『TRAVELLER』経験者にとっては懐かしくまたなじみ深い設定となっています。
本ゲームのルールブックにはこうした基本知識についてのガイドが用意されていますので未経験者でも、本ゲームをプレイする上での支障はありません。
プレイヤーは「銀河帝国」(以後、帝国、帝国軍)か、「ゾダニ / ソードワールド / ヴァルグル」連合軍(以後、連合国、連合軍)のいずれかを担当します。
ユニットには、艦艇(小艦隊)ユニットの他、陸上ユニット、それらを指揮する複数の提督ユニットが登場します。他にそれぞれの星系固有の防衛組織として陸上部隊や、惑星防衛艦隊(System Defence Boats: SDB)が設定され、その星系が戦場になると登場します。
『TRAVELLER』は基本的な設定がハード寄りの真面目なSFのため、その世界観の中に、超兵器・とんでも兵器が登場する訳ではありません。とはいえ『航空宇宙軍シリーズ』(谷甲州)や『TRIPLANETARY(三惑星連合軍)』(GDW / Steve Jacson Games)のようなキレキレでプリミティブなハードSF系世界というより、『銀河英雄伝説』(田中芳樹)のようなシリアス系スペースオペラ風味の世界観と言ったほうがよいかもしれません。
古今東西、有形無形・人造/天然の超兵器・トンデモ兵器、超能力、古代の超文明などが秘密兵器やイベントとしてゴロゴロと頻出する宇宙を舞台にしたマルチプレイヤーの作品です。各プレイヤーによって目的とする勝利条件は異なるのですが、宇宙艦隊は重要な要素であり、星間戦争は頻発します。『TRAVELLER』『第五次辺境戦争』が扱う宇宙戦争とはまた異なる趣きの作品です。
本作の世界を形作るキーワードとSF的世界観
『第五次辺境戦争』のゲームシステムを特徴づけるいくつかのキーワードをあげます。
- ジャンプ能力…「小艦隊」ユニットのパラメータのひとつ。そのユニットが移動時に移動(ジャンプ航法=ワープ航法)できるヘックス数(1ヘックス=1パーセク=3.26光年)を表す。ジャンプエンジンを搭載している「小艦隊」ユニットは2~5の数値を持ちます。
- 燃料補給タイプ…「小艦隊」ユニットのパラメータのひとつ。その艦艇の形状を表し、燃料補給が可能な場所の制約や燃料補給に必要となる拘束期間が性能差として表されている。
- 計画移動値…「提督」ユニットのパラメータのひとつ。その「提督」が指揮する艦隊について、事前にプロットしなければならないターン数を表す。例えば計画移動値が「3」の提督の場合は、「3」ターン先のアクションをプロットしなければならず、今プロットしたアクションは「3」ターン先になってはじめて実行される。計画移動値が「0」の提督も稀に登場するが、この場合、事前プロットは不要となる。
- テクノロジーレベル…陸上ユニットや星系毎に設定されるパラメータのひとつ。装備している兵器の技術レベルを表し、「0」は石器時代、最大値の「15」は現在の最新鋭技術(<帝国>の最新鋭技術)、1981年のアメリカの技術は「8」となる。戦闘時には彼我の部隊のテクノロジーレベルの差の分、戦闘解決表上で戦闘比率のシフトが発生する。

マップの全景。白い点が星系があるヘックスを表す。
赤色ユニットが<銀河帝国>、青色が<ゾダニ評議国>の艦隊か小艦隊を表すユニット。<ヴァルグル連合>(橙色)と<ソードワールド連合>(緑色)は写真の上側と下側に少数登場している。
赤色と青色の線がそれぞれの政治的な領有の境界線。
<ゾダニ>の一部ユニットが<銀河帝国>の領宙内に侵入しているのがわかる。
艦隊ユニットは移動にあたって、星系がない全くの虚無のヘックスではなく、星系があるヘックスをだどっていく必要がある。そこで登場するのが前述の「ジャンプ能力」となり、ジャンプ能力の数値以内に星系がない場合はその小艦隊ユニットはどこにも移動できないことになる。
マップの両端に並んだ四角の枠は、マップ内に存在する星系事に用意されており、駐留している陸上部隊や小艦隊ユニットが置かれている。配置されたユニットとは別に各星系には固有の陸上部隊や惑星防衛艦隊(SDB)が存在する。

「小艦隊」ユニットとそれらが搭載/輸送している陸上ユニットは、艦隊としてまとめられている。マップ上には艦隊を表すマーカーが配置される(マップ上に直接、「小艦隊」ユニットを配置することも可能)。
艦隊はその行動の考慮すると前述の「ジャンプ能力」や「燃料補給タイプ」毎にまとめられている方が良い。そうでなければ、いくら性能が良い「小艦隊」ユニットも、移動においては同じ艦隊内に配置された性能が劣るユニットに足を引っ張られることになる。
艦隊番号が通番ではなく、第40艦隊とか、第17辺境艦隊とか第1強襲艦隊とか適度にばらけているのがそれっぽくてそそります。
『TRAVELLER』世界(=本作の背景世界)の恒星間航行はジャンプエンジンを搭載した宇宙船によるジャンプ航法(=ワープ航法)に依るのですが、ジャンプできる距離が2から5ヘックス(=2~5パーセク)に限定されるのが特徴です。*1
距離に制約があるため、例えばマップ上の境界線からマップの中心に位置する<リジャナイナ>(<帝国>領の星域首都がある惑星)までいくまでも何度もジャンプを繰り返さなければならないことになります。
超空間通信やワープ通信のような光速を越えた通信を可能とする技術は実現されていないことから、恒星間の通信は江戸時代の通信が飛脚に依っていたように、メッセージを携えた通信艇(Xボートと呼ばれる)に依存しています。
結果として、艦隊を指揮する<提督>に対しては事前プロットとなっています。中には、平家討伐軍を率いた源義経のように現場で即妙即断する<提督>(=「計画移動値」がゼロ。事前プロット無しにアクションを実行可能)がいる一方で、いちいち鎌倉にお伺いをたてなければならないような「計画移動値」が「4」(=4ターン先のアクションまでプロットする)の<提督>までが混在しているという世界観です。
ゲームシステム
シーケンスはシンプルです。
- 増援フェイズ
- 移動フェイズ...ダイスによってイニシアティブを決め、あらかじめプロットされた内容に従って移動等のアクションを実施する
- 戦闘フェイズ...移動の結果、両プレイヤーのユニットが同一ヘックスに存在した場合、戦闘になる。戦闘は同時解決。
- 再編成・計画フェイズ...部隊の再編成、また「計画移動値」に定められた先のターンにおけるアクションをプロットする
移動はプロットに依ります。移動後、戦闘を解決し、その後、数ターン先のためのプロットを記録するというのがターンの流れになります。
移動の結果、同一ヘックス(=同一の星系)に両軍のユニットが存在した場合、戦闘が発生します。
戦闘は細かく段階を踏みます。小艦隊と書いている場合、艦隊としてまとめられている場合を含みます。
- 宇宙戦闘ステップ...小艦隊 対 小艦隊
- 惑星戦闘ステップ
a. 小艦隊 対 惑星防衛艦隊(SDB)
b. 小艦隊 対 地上部隊、またはSDB 対 地上部隊(揚陸後の)
c. 小艦隊から地上部隊の揚陸、または小艦隊への搭乗- 地上戦闘ステップ...地上部隊 VS 地上部隊
※ 小艦隊というのは複数の艦艇からなる艦隊を構成最小単位で、
ゲーム内では1個のユニット(駒)で表されます。
小艦隊が集まったのが「艦隊」ですので、上記は「小艦隊」を「艦隊」と
読み替えていただいてよいです。
ある敵勢力圏内の星系に艦隊が侵入すると、その星系に敵艦隊が存在していた場合、対艦隊戦が行われます。ここでは「戦艦」「巡洋艦」などが活躍することでしょう。戦闘はどちらかが全滅または撤退するまで続けられます。
侵攻側が勝利した場合、続いてその星系固有の惑星防衛艦隊(SDB:System Defence Boats)との戦闘に移行します。SDBは星系内の防衛を任務としている外宇宙航行能力(=ジャンプ能力がない)艦隊であると想像されます。
SDBは星系によって、数十隻から一番多いところで1000隻を擁しています。SDBとの戦闘において先に書いた「テクノロジーレベル」(星系毎に設定)の差がダイス修正としてはいります。イメージとしては『宇宙戦艦ヤマト』冒頭の地球侵攻を企てるガミラス艦隊に対する外宇宙航行能力を持たない地球防衛艦隊との戦闘のようなものでしょうか。
SDBの排除に成功すると続いて星系の地上部隊に対する爆撃を行います。軌道上の宇宙船から地上に向けて使われる”プラネット・ボンバー”*2のようなものでしょうかね。
その後、陸上部隊の揚陸が実施されます。選択ルールとして、「降下部隊」も登場します*3。陸上部隊の輸送は「戦艦」「巡洋艦」でも可能ですが、大兵力の輸送には「強襲揚陸艦」が必要です。
その後、陸上部隊同士の戦闘が行われます。星系の占拠のためには陸上部隊を全滅させなければなりません。最後を決めるのは歩兵?なのです。
陸上部隊はその兵装が星系の「テクノロジーレベル」に依存しており、人数は星系によって異なります。多くて数千人という規模の星系がほとんどですが、中には15万人の兵力を抱える星系もあります。
陸上部隊同士の戦闘では、「テクノロジーレベル」のレベル差が、戦闘解決表の解決欄のシフト数として扱われるため、レベル差がある軍隊同士の戦闘においては、100人対1万人といった兵力差であっても勝敗がひっくり返されることが起こります*4。
なお戦闘解決には戦術的な要素はありません。戦闘方法によって解決に用いる表は異なるのですが、基本的には攻撃力合計値や攻撃力比率を用いてダイスロールすることになります。
小まとめ
艦隊毎に必要プロット数が異なる移動システム、艦隊戦から地上戦闘まで何段階にもわたる戦闘解決などSFファン視点ではとても面白いのですが、プレイアビリティという点では煩雑なのは事実です。
元がTRPGのためかプレイする上での親切度は高くありません。もちろん戦闘解決表など必要な情報は提供されているためゲームとして回すには事足りているのですが、スムーズに実施するための手段(プレイエイド、早見表、各種マーカー類など)は一般的なTRPGと同じくゲームマスターが創意工夫をするものだ、といった感じの突き放し方に見えました。
実際にプレイしてみて、スムーズなプレイのためにはマーカー類を自作することをオススメします。
こんなマーカーがあればよかったな・・案
■ 艦隊の燃料補給済/未済のマーカー(マップ上に艦隊マーカーとあわせて配置)
宇宙戦闘において小艦隊ユニットは戦闘からの「離脱」を試みることができるのですが、この際、燃料補給済か未済かで成否が決まります。
この際「燃料補給タイプ」と、どのタイミングで艦隊がその星系に到着していたかが関係します。艦型が流線型の場合はガスジャイアントまたは海洋を持つ惑星がある星系であれば即補給されていますので、燃料補給済と判断されるのですが、非流線型や部分流線型の小艦隊の場合は、その星系に到着したばかりなのか、もともと存在したのかによって燃料補給済か未済なのかが分かれ、結果として「離脱」成否が決まることになります。
■ 星系のステータスを表すマーカー(マップ上に配置する想定)
ゲームスタート時、帝国をはじめ各国領内の星系は当然、それぞれの支配下にある訳ですが、ゲームが進むにつれ、あちこちで戦闘が発生し、支配関係が変わったり、戦闘状態が続いた状態であったりとそれぞれのステータスはかなり変わってきます。都度、マップ脇の星系のボックスを見に行くことで戦闘中や占領済などわかるといえばわかるのですが、毎回のようにボックスを確認するのもかなり手間です。特に中立宙域の星系や、重要度が低いマイナーな星系の場合、戦闘が終わってしまい、小艦隊ユニットなども残っていない場合など、支配関係の変更などが起こっていないのか、すでに戦闘などが終わった後なのかなど忘れてしまう・・ことが起こりがちです。
星系を表すボックスは地理的要素少なめで並んでいることもあるため、それぞれの星系の支配関係やステータスをマップ側にも示すことでかなり手間を省くことができるでしょう。
付録:TRPG『TRAVELLER』におけるテクノロジーレベルについて
『TRAVELLER』世界に通暁されているGEMINIさんに訊いてみました。
テクノロジーレベルは、一般的に0から15までの数値で表されますが、詳細な設定は版やサプリメントによって異なる場合があります。ここでは、一般的な傾向をいくつかご紹介します。
-
レベル0-3:
-
レベル4-7:
-
レベル8-11:
-
レベル12-15:
- 超文明: 物質転換や時空操作が可能になるなど、科学技術が神に近いレベルに達する。宇宙全体を支配する帝国が誕生する場合もある。
- 宇宙船の設計: テクノロジーレベルによって、利用可能なエンジンや武器、シールドの種類が制限される。
- 装備: 利用可能な武器や防具、通信機器などが変化する。
- 社会構造: テクノロジーレベルが高いほど、社会は複雑化し、階層構造が明確になる傾向がある。
- 文化: 技術の発展に伴い、芸術や哲学などの文化も変化する。
具体的な例
- レベル5の惑星:
- 産業革命期に相当する技術レベル。
- 主要な動力源は石炭や石油。
- 鉄道網が発達し、大陸間の移動が可能。
- 大都市ではスラム街が形成され、社会問題が深刻化している。
- レベル10の惑星:
- 宇宙時代における高度な文明。
- 宇宙船による恒星間航行が日常的に行われている。
- 人工知能を搭載したロボットが普及し、人間の労働を代替している。
- 遺伝子操作によって、人間の寿命が大幅に延びている。
まとめ
TRPG『TRAVELLER』のテクノロジーレベルは、単なる数値ではなく、その惑星における歴史、社会、文化を包括的に表現する指標です。プレイヤーは、このテクノロジーレベルを参考に、キャラクターのバックグラウンドやプレイスタイルを決定することができます。
(つづく)