近い将来起こり得るかもしれないバルト海での軍事紛争を扱った『LITTORAL COMMANDER THE BALTIC』(The Dietz Fundation)を対戦しました。シリーズ第2作、アメリカ軍の相手になるのはロシア軍です。今回は練習シナリオとされているバルト海のゴットランド島を舞台にしたシナリオ「遭遇戦:ゴットランド奪回作戦 – Meeting Engagement: Gotland Redux」を選びました。
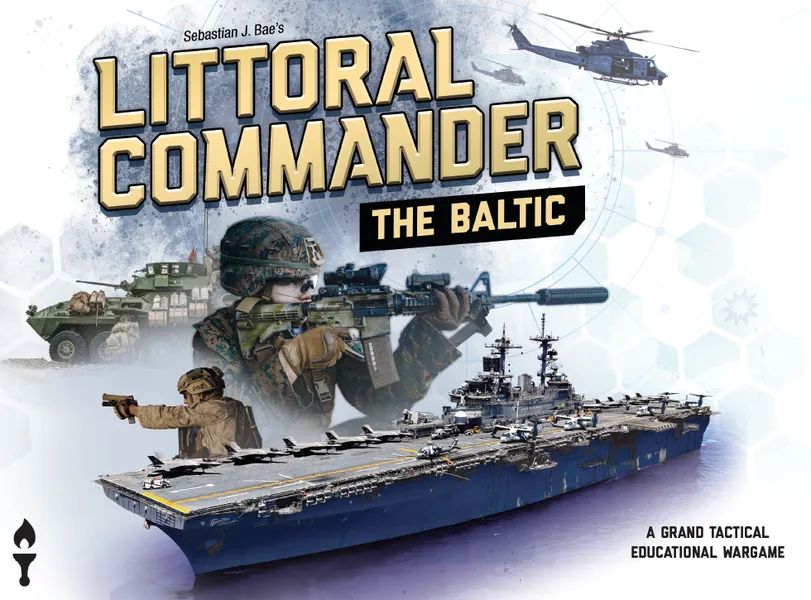
背景:バルト海の天元を巡る戦い
20XX年、NATO軍とロシア連邦軍との広範囲な地域紛争が北欧全域に拡大する中、ロシア軍は、バルト海における航空作戦の拠点確保を企図した。目標はスウェーデン領ゴットランド島――バルト海中央に位置し、半径500キロメートル圏内の制空権を左右する戦略要衝である。
島内のヴィスビー飛行場(Visby Airport)を確保すれば、北欧戦線全域の友軍部隊に対する航空支援が可能となる。ロシア軍はこの戦略目標達成のため、海兵部隊を投入した。上陸作戦は計画通りに進行し、ロシア軍は島内の主要施設を次々と制圧していった。スウェーデン軍守備隊の抵抗は続いたが、ロシア軍は着実に支配地域を拡大した。
シュトゥットガルトの米欧州軍司令部(USEUCOM)は、事態を重大な戦略的脅威と判断した。ゴットランド島がロシア軍の手に落ちれば、バルト海全域のパワーバランスが崩壊する。
USEUCOMは即座に対応部隊の派遣を決定した。最も近い位置にいた水陸両用即応グループ(ARG)と、その配下の海兵遠征隊(MEU)に出動命令が下された。
強襲揚陸艦USSワスプを旗艦とするARGは、ただちに北方海域へ針路を取った。艦内では作戦計画の最終調整が進められ、隊員たちは装備の点検と作戦ブリーフィングに臨んだ。
海兵遠征隊に与えられた任務は明確だった。ゴットランド島を占拠したロシア軍を撃破し、島の支配権を奪還すること。
島内のロシア軍は既に防御陣地を構築しており、上陸地点は対艦・対空火器の射程内にある。制空権も不確実だ。だが、作戦は実行されなければならない。
バルト海を北上する艦隊では、上陸準備が粛々と進められていた。戦いは間近に迫っていた
ゲームの紹介
「LITTORAL COMMANDER」を直訳すれば「沿岸戦闘司令官」となります。本作は単なるウォーゲームではなく、現代軍事ドクトリンの変革を反映した教育的側面も持つシミュレーションです。
背景となる軍事思想:Force Design
本作の基盤となっているのが、アメリカ海兵隊が2020年3月23日に発表した「Force Design 2030」(略称: FD2030)です。
この計画は、海兵隊の戦闘力を根本から再構築し、中国やロシアといった近接大国との戦略的競争に対応するためのものです。伝統的な陸上中心の重装備型部隊から、軽量・機動性が高く、海洋遠征戦(Naval Expeditionary Warfare)に特化した部隊へのシフトを目指しています。
現在(2025年時点)では「Force Design 2030」という名称から「Force Design」(FD)と簡略化され、計画は継続中です。
本作シリーズはこのFDによって改組改編された近未来の海兵隊と、それに対抗する仮想敵が登場する作品となっています。
ゲームシステムの特徴
スケールと表現
- 陸上兵力:1個小隊単位
- 艦艇:フリゲート艦以上の主要艦を1隻単位で表現(潜水艦はカードとして登場)
- 航空戦力:カードとして抽象化
- 時間スケール:1ターン=2~3時間
カードシステム(JCC)
両軍が装備している各種兵器・装備や取り得る戦術(ドクトリン)などは全てカード(JCC: Joint Conflict Card)として提供されています。このカードシステムこそが本作最大の特徴です。
カードで表現される要素(例):
- 各種無人兵器(ウクライナ戦争で名を馳せたドローン類)
- サイバー攻撃・防御
- 弾道ミサイル等のスタンドオフ兵器
- 監視衛星などの宇宙空間の兵器
- 各種航空機・ヘリコプター
- 偵察手段(偵察機、ドローン、衛星、気球、OSINTなど)
プレイの流れ
プレイヤーはゲーム開始前に、シナリオで指定されたカードの他、与えられたポイント内でカードを購入します。
陸上部隊と艦艇だけが登場する盤面は従来のウォーゲームと比べてシンプルですが、盤外にこうしたカード類が並び、戦闘の中心となります。

盤面に比べると番外のカード(これ以外にリソース管理のカードがあります)のほうがうるさいことになっています。
盤面のユニットは青がアメリカ軍、赤はロシア軍です。まだ両方とも未探知状態なので、裏返されています。
重要な点:ゲーム開始前のカード選択こそが勝敗を分ける
スタート後の盤面展開は、選んだカードが正解だったかを確かめる"答え合わせ"の場面に過ぎないとさえ言えます。カード選択の段階が本作のメインと言っても過言ではありません。
シナリオのシチュエーションや現有兵力に対して、どのようなカードを携えていくのか――その選択によっては、相手が繰り出したカードによる攻撃や兵器に対する対抗手段がなく、これ以上展開できないという"詰み"の状態に陥ることがあり得るのです。
「探知」の重要性
作中に登場する各種兵器に共通して言えるのが、相手部隊を「探知」することの重要性です。
探知なくして攻撃なし ――これが本作の鉄則です。
「探知」の方法は視界内での移動などによる発見もありますが、ミサイルの交戦距離での戦闘では例えば以下のような手段を講じる必要があります。
これらの多くはカードとして提供されます。
しかし、いったん「探知」されてしまうと即座に攻撃対象となります。つまり、ミサイルが各所から飛来するのです。ミサイル兵器はマップ上のどの場所にいても射程内として攻撃対象になりえます。ミサイル攻撃に対してはミサイル防衛システムを発動させる必要があります。
ゲームデザインの哲学
全体として、カードで提供される各種兵器等は詳細に描写される一方、ゲームの基本メカニズムはプレイアビリティを考慮して比較的シンプルに設計されています。
これは本作がいわゆるウォーゲーマーだけでなく、教育用として非ウォーゲーマーがプレイすることを考慮しているためと思われます。実際、軍事教育機関での使用も視野に入れた設計となっていると聞きます。
レポート
対戦相手はロシア・ソ連への愛が止まらないZ氏です。このため3戦とも当方がアメリカ軍を担当しています。
シナリオ設定
- 期間:全3ターン(短期決戦の練習シナリオ)
- 勝利条件:
両軍 ゲーム終了時の撃破ユニット毎に1VP
アメリカ軍は島に上陸したユニット毎に1VP
兵力
ロシア軍:
アメリカ軍:
- 強襲揚陸艦USSワスプ(1個中隊強の海兵隊が搭乗、航空戦力や上陸用の装備(カードとして登場)を搭載)
- イージス駆逐艦USSアーレイ・バーク
- イージス駆逐艦USSルーズベルト
- 16ポイント分のカード(うち10ポイント分は指定)
第1戦:海上戦力の圧倒
アメリカ軍の戦略
3ターンしかないことから時間的余裕はないと判断。また搭載ミサイル数の優位から、ロシア艦隊との撃ち合いでも勝算ありと見て、駆逐艦を積極的に南下させる作戦を選択しました。
戦闘経過
海上では陸上と異なり有視界距離が長く、すぐにロシア艦隊を発見。直ちにミサイル戦闘に移行し、ロシア艦2隻を撃破しました。
並行して、ワスプより発進した航空隊が島内に展開したロシアの対艦攻撃能力を持ったミサイル部隊を発見し、これも撃破に成功しました。
結果
ロシア軍は上陸後の地上戦を想定したカード構成にしていたようで、アメリカ軍の海上戦力に対する有効な攻撃手段に乏しかったことが判明。アメリカ軍は上陸をすることもなく撃破数でロシア軍を上回ったことにより終了
勝者:アメリカ軍

島南沖合で両軍の艦艇が接近。アメリカ軍はミサイル戦力にものをいわせてロシア艦に接近しています(ロシア側がその前にミサイルをほとんど撃ち尽くしていた事情もあり)
第2戦:対艦戦闘への適応
ロシア軍の修正
ロシア軍は第1戦の反省から対艦戦闘を意識したカード構成に変更。地対艦ミサイル「バール」(Бал)を投入しました。
アメリカ軍の対応
アメリカ軍も第1戦の反省から「探知」能力のさらなる向上を目指した構成に変更しました。
戦闘経過
ロシア軍が放った地対艦ミサイル「バール」に対し、アメリカ軍は迎撃に成功。イージス駆逐艦2隻がロシア艦隊を制圧した後、ワスプが南下し、島北方からボートと空中機動により陸上部隊を揚陸しました。
ロシア軍陸上部隊が島南部に集中配置されていたため、北方からの上陸に対する有効な迎撃ができませんでした。
勝者:アメリカ軍

アメリカ軍は沖合のロシア艦艇を無力化すると、強襲揚陸艦が島北方に接近、海兵隊部隊の揚陸に成功します。
第3戦:ワスプ被弾
アメリカ軍の積極策
第1戦・第2戦の成功を受け、アメリカ軍はより積極的にロシア艦隊との接触を図りました。島影に隠れるロシア艦艇を追い、イージス艦は島の西海域を南下。あわせてワスプも早期に島へ接近させました。
致命的な誤算
これが悪手でした。
第2戦よりも強化されたロシア地上部隊の対艦攻撃に対し、ロシア艦隊を追って島南沖に移動していたアーレイ・バーク他のイージス艦は防御対象のワスプとの距離の関係で十分な迎撃体制を取れませんでした。
ファランクスCIWSの迎撃をも逃れた1発の対艦ミサイルがワスプに命中。上陸準備をしていた海兵隊部隊を含め、甚大な被害を受けてしまいました。
ネットワーク攻撃の追い打ち
いったんワスプ他は沖合に退避し、最終ターンでの反撃態勢を整えようとしました。
しかし――ロシア軍が実施したサイバー攻撃(ネットワーク攻撃)が成功。ワスプとその搭載機、海兵隊部隊はそのターン行動不能に陥ってしまいました。
勝者:ロシア軍
感想戦:カード選択こそが全て
戦略の深さ
上述したようにマップ上は地味ですが、カードを使った戦闘はその選択も含めてかなり考えさせられます。
両軍ともそれぞれ200枚近いカードが用意されているため、その中から何を選ぶのかは重要な判断となります。
これが非常に面白い。前作、「Indo-Pacific」ではそこまで思わなかったのですが、いわばデッキを組み上げる感覚ですが、カード内容をある程度詳しくなってからではないなとこの面白みはなかなかわかりづらいです。
ロシア軍の研究勝ち
3戦を通じて、ロシア軍の研究勝ちといったところでしょう。
特に第3戦では、アメリカ軍の積極策に対してネットワーク攻撃という非対称戦力を効果的に投入し、戦況を一変させました。これは現代戦におけるサイバー戦の重要性を如実に示すものでした。*1
補足:ゴットランド島について
戦略的重要性
今回のシナリオの舞台となるゴットランド島は以下の地理的特性を持ちます。
この位置関係から、ゴットランド島はバルト海の制海権・制空権を握る上で極めて重要な地点となります。
意外な島の大きさ
今回記事を書くにあたりゴットランド島の面積を確認したところ、イメージとはかなり異なる事実が判明しました。
ゴットランド島の面積は沖縄本島の2.5倍以上
日本近海にある島々と比べるとかなり大きなサイズであることがわかりました(当方も正直、かなりびっくりしました)。
現実の軍事情勢
2024年のスウェーデンのNATO加盟により、ゴットランド島はNATOの防衛体制に組み込まれました。
現在、スウェーデン軍はゴットランド島に通常部隊に加え、「ホームガード」と呼ばれる市民兵を含む部隊を常駐させています。また、アメリカ軍との合同演習も実施されています。
ホームガードについて: スウェーデン軍における「ホームガード」は、民間人が非常時に軍事任務を担うために編成された地域防衛部隊です。訓練頻度などを調べると、日本の予備自衛官に近い位置づけと言えそうです。
デザイナーからのコメント:自衛隊の登場予定
今回のプレイ報告をXに投稿したところ、デザイナー氏ご本人からコメントをいただきました。その中で、かわぐちかいじ氏の漫画『空母いぶき』で描かれた先島諸島での戦いを本作で扱えるのではないかと話したところ、自衛隊も次次作(シリーズ第4作)で登場する予定との情報をいただきました。
東シナ海や南西諸島を舞台にし、日本の水陸機動団などが登場する防衛シナリオがプレイできる日が来るかもしれません。今から非常に楽しみです。
『LITTORAL COMMANDER: THE BALTIC』(The Dietz Foundation)を対戦。2030年の米ロ激突がテーマ。練習用シナリオ「ゴットランド島奪還」を3回プレイ。リアルな戦場だけでなく、宇宙やサイバー空間まで広がる戦場や各種兵器・技術をカードで表現することで、#ウォーゲーム #ボードゲーム #Wargame pic.twitter.com/oL7GaBxRrd
— yuishikani (@yuishikani1) 2025年11月2日
次の「LC:IP 2025年版」には沖縄マップの離島に双方が上陸をもくろむ相互上陸シナリオが追加されました。また先島諸島~台湾北部~中国沿岸を収録した「Ryukyu West」マップの試作品は3年前から存在するので、たぶん次の次の自衛隊モジュールには収録されるんじゃないかと期待しています。 https://t.co/LYT2zr7AF4
— N村 (@enumura) 2025年11月6日
The Southwest Islands / Sakishima islands will definitely be in LC JAPAN
— Sebastian Bae (@SebastianBae) 2025年11月6日
Aircraft Carrier Ibuki is such a great series! I am currently working on LC JAPAN and it will feature both the Southwest Islands so look out for it 😁
— Sebastian Bae (@SebastianBae) 2025年11月6日
(終わり)