1942年の東部戦線、「冬の嵐」作戦を題材とした作戦級ウォーゲーム『DONNERSCHLAG』(VUCA Simulations)を対戦しました。1942年12月、包囲下にあったスターリングラードの第6軍を救出するべくマンシュタイン元帥が率いるドン軍集団(Army Group Don)が実施した「冬の嵐作戦」(Unternehmen Wintersturm)を扱った作戦級ゲームです。同テーマの作品は大小様々に存在する人気テーマです。
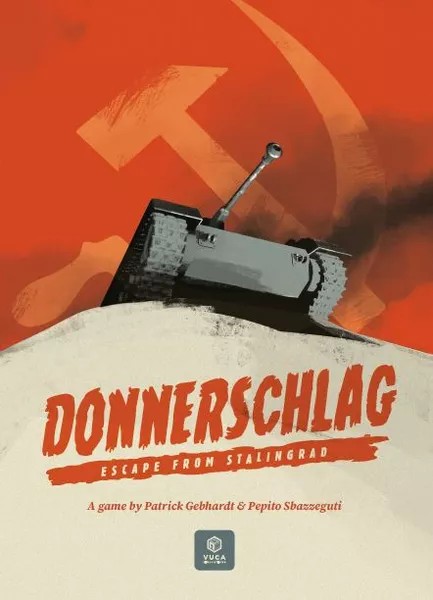
ゲーム概要
スケール
 1ヘックス=4キロ、1ターン=2~3日
1ヘックス=4キロ、1ターン=2~3日
1942年12月12日から23日の全8ターン*1。
ユニット規模はソ連軍とルーマニア軍が旅団ないし連隊単位、ドイツ軍は大隊または中隊単位になります。
基本システム
 カードドリブン方式を採用しており、両軍はカードを用いて交互に活性化を実施します。活性化するとカードに記載されたグループの部隊ユニットが移動と戦闘が可能となり、グループ単位で移動を行った後、戦闘を実施するという構成となっています。
カードドリブン方式を採用しており、両軍はカードを用いて交互に活性化を実施します。活性化するとカードに記載されたグループの部隊ユニットが移動と戦闘が可能となり、グループ単位で移動を行った後、戦闘を実施するという構成となっています。
活性化は、枢軸側は師団(ドイツ軍)または軍団(ルーマニア軍)単位で実施します。一方、ソ連側は各ユニットにおいて複数の活性化方式が可能であり、軍司令部が機能し始めるまでは、より小規模な軍団単位、あるいは(最も頻繁に使用されるのですが)カラー単位での活性化となります。
カラー区分とは、すべてのソ連軍部隊ユニットに表示された赤・青・黄・緑の4色のことを指します。この分類に特段の意味合いはなく、ランダムに割り振られている様子で、初期配置およびその後の増援で登場するソ連軍ユニットはそれぞれ不規則に4色のいずれかのラインが表示されています。例えば「赤」グループに属するユニットはマップ全体に分散しており、特定地域の部隊を後退させる、戦線を形成するための連携した移動、戦力の集中といった統制のとれた行動が困難となっています。これはソ連軍の統制の欠如を巧みに表現したルールといえるでしょう。
両プレイヤーは各ターン開始時に「活性化カード」と、戦闘やその他のタイミングで発動可能なイベントが記載された「戦闘カード」をそれぞれ5枚ずつ手札とします(ゲーム進行に伴い、この手札制限は変動します)。「活性化カード」には前述のような活性化可能なグループが記載されており、基本的に両勢力とも毎ターン5回ずつ活性化を行うことになります。同一グループが同一ターン内で複数回活性化されることも可能です。
部隊ユニットは装甲(戦車)、自動車化、歩兵の3種類に分類されます。装甲(戦車)のみが戦闘後前進可能である(これは戦術上相当な影響を与えます)一方、通常移動において橋梁が存在しないヘックスでは河川越え移動に制約があります(自動車化ユニットは全移動力で河川を越えられます)。
ZOCは弱ZOCであり、敵ZOCからの脱出、敵ZOCから直接別の敵ZOCへの移動も認められています。
戦闘ルール
 戦闘は戦闘力比率に基づき6面ダイス1個で解決されます。「戦闘カード」には戦闘時やその他のタイミング(カードに指定されている)で発動可能なイベントが記載されており、多くのイベントはダイス判定による成否判定の上、効力を発揮します。
戦闘は戦闘力比率に基づき6面ダイス1個で解決されます。「戦闘カード」には戦闘時やその他のタイミング(カードに指定されている)で発動可能なイベントが記載されており、多くのイベントはダイス判定による成否判定の上、効力を発揮します。
戦闘結果は一般的なステップロス数と後退が組み合わされた内容ですが、特筆すべきはダイスの目によっては両軍とも部隊ユニットが盤上に発生する点です。
ドイツ軍が攻撃を実施した際に修正後のダイスが1以下の場合、ソ連軍は増援ユニットとして補充兵ユニット1個を入手し、マップ上に配置することが可能となります。
逆にソ連軍が攻撃を行い、ダイスが6以上となった場合、ドイツ軍側に歩兵ユニット1個*2が登場します。
戦闘効果として、装甲(戦車)ユニットが参加した場合に得られる「戦車効果」と、装甲(戦車)ユニットと自動車化歩兵ユニットが同時に攻撃に参加したときに得られる「複合兵種」の効果によりそれぞれ戦闘結果表を1シフトさせる効果があります。
その他の兵種や航空支援、陣地構築といった要素は登場しません(カードイベントとして記載されることはありますが、特定の部隊ユニットが出現するものではありません)。登場する陸上ユニットの能力は同種のユニット間で均質化されています。後述するように、戦闘力の計算や部隊配置などにおいて迷う要素は少なく、プレイアビリティの向上には寄与していますが、特徴に乏しい同質のユニットが並ぶ状況にもつながっています。
勝利条件
 勝利条件は明確です。ゲーム開始時にドイツ軍が配置された場所とは反対側に設定されたエリアに到達することで、スターリングラードで包囲された第6軍と邂逅したとみなされ、ソ連軍の包囲網を解囲したことになります。
勝利条件は明確です。ゲーム開始時にドイツ軍が配置された場所とは反対側に設定されたエリアに到達することで、スターリングラードで包囲された第6軍と邂逅したとみなされ、ソ連軍の包囲網を解囲したことになります。
邂逅エリアは3箇所用意されており、あらかじめ邂逅するエリアを指定する必要があります。
ドイツ軍プレイヤーはスターリングラードで包囲されている第6軍側が発動する「雷鳴」作戦の発動を宣言することができます。作戦が発動すると同時に邂逅エリアが指定され、発動の4ターン後までにマンシュタイン側のドイツ軍ユニットが指定された邂逅エリアに1ユニットでも到着すると、ドイツ軍の勝利、それを阻止するとソ連軍の勝利となります。
なお、第6軍側の部隊ユニットは本ゲームには登場しません。
プレイ
ソ連軍を担当した
初期配置

マップは上側が西方向、ドイツ軍はスタート地点から北東方向(右方向)に進撃することになる。初期配置は両軍とも決まっている。マップ左側のコテリニコボ(Kotel'nikovkiy)周辺には出撃を待つ枢軸軍が展開している。ソ連軍はマップの縦方向に流れる、左から、アクサイ・クルモヤルスキー川(Aksay Kurmoyarskiy)、アクサイ川(Aksay River)、ムイシコワ川(Myshkova River)の3本の川沿いに展開している状態。
スターリングラードはマップ右端に見切れており、マップ右手に、大きくA・B・Cと描かれたエリアがスターリングラード(マップ右端)の第6軍と邂逅するエリアになる。
ドイツ軍はゲーム途中で遅くとも第4ターンまでに「雷鳴」作戦(スターリングラードからの脱出作戦)の発動を宣言し、同時にソ連軍に隠した状態で邂逅エリアを指定する。
作戦展開を考える上で次のような特徴から、各河川に複数箇所存在する渡河点が争奪の対象となる。
- 戦闘後前進を実施できるのは装甲(戦車)ユニットのみ
- 第二次移動のような戦線突破を実施可能な移動はない
- 装甲(戦車)部隊は橋梁がある渡河点を介してのみ川を渡ることができる
第1ターン

ドイツ軍の主力は第6装甲師団と第23装甲師団、途中、第17装甲師団が増援として追加される。活性化のためのカードは毎ターン5枚受領するが、配下部隊がバランス良く活性化できるような構成でドローできることは少ない。このときも枢軸軍は第23装甲師団とルーマニア軍の歩兵軍団の活性化カードばかりがドローされたことから、第6装甲師団(盤面奥側に展開)の活動開始は次のターンにずれ込むこととなった。
ソ連軍はてんでバラバラに設定されたカラーコード毎の活性化となるため、同じ戦線を作る部隊ユニット同士が同じタイミングで動き出しができることのほうが珍しく、結果として戦線の整理、渡河点の確保、後方にいる部隊の前進配備などに費やされた。
第2ターン

ドイツ軍は第6装甲師団(画面奥側)が集中的に活性化を実施、大きく前進する。1か所、渡河点を占拠し、アクセイ川(左から2番目の川)を突撃砲中隊が突破している。ソ連軍はカラーコード毎の活性化により前線に取り残される部隊ユニットがどうしてもでてしまうなど、個別に撃破されていく。戦線の大崩れは防ぐように、薄いながらも戦線を張る。
第4ターン

枢軸軍は「雷鳴」作戦の発動を宣言、4ターン先の第8ターンに指定した邂逅エリアに到着する必要がある。
枢軸軍は第6・23装甲師団を先頭に進撃、左からアクセイ川を渡河している。A地点で退却が遅れたソ連軍の一団がアクセイ川の南側に取り残された。本ゲームでは、各部隊ユニットはそれが属するグループが活性化された際に補給判定がされる。B地点にあたるVerkhnekumsky(史実でもここは両軍の争奪の対象となり激戦が交わされた)はこの後、包囲されるのだが、「戦闘カード」の効果もあいまってソ連軍の防衛部隊が善戦することでドイツ軍に思わぬ足踏みをさせることとなる。
全体傾向として枢軸軍の進撃はマップ奥側に集中していることから、ドイツ第6軍との邂逅地点はAエリアまたはBエリアになることが想定された。本ゲームの勝敗はエリアへの到着状況だけで判断されることから、ソ連軍もマップ手前側に配置していた部隊ユニットをドン河に近い西側に移動させていく。
ソ連軍に軍司令部ユニットを配置可能というカードが2枚くるが、軍司令部ユニットの指揮範囲が広くないため、同じカード内に記載された、増援ユニットの受領イベントとしてカードを使ってしまった。その後、ゲームを通して、軍司令部ユニットの受領に関するイベントカードは2度とドローできなかったが、ゲームの進行上、さほどの影響はなかった・・。
第5ターン

枢軸軍はVerkhnekumskyの攻略は諦め、包囲しながら主力は北上させる。ますます進撃ルートが東方向へ偏っていることが目立つようになり、邂逅地点はAエリアまたはBエリアである可能性が高まった。
ソ連軍の布陣は中央部が厚く、ドン河沿いの防御が手薄であったため、急ぎ部隊を転送する。ここで増援として登場する部隊ユニットの登場のさせ方の間違いに気づく。本来ルールであればもっと手早く増援の部隊ユニットを前線に展開できるはずであった。
ソ連軍はアクセイ川の南岸で部隊を前進させるが(赤矢印のライン)、本作の場合、補給判定や補給切れのルールがゆるいため、この進撃自体が枢軸軍への痛撃とまではいかない。またアクセイ川南岸に取り残されていた部隊ユニットはほぼ全滅している。
第6ターン

ドイツ軍の最西翼(ドン河に近い方)を進む第6装甲師団、第17装甲師団はムイシコワ川の南岸にとりつき、同川の渡河点への攻勢を行う位置についた。
対するソ連軍はムイシコワ川沿いの防衛を強化するのとあわせ、部隊を足止めができるように部隊を展開させた。
第23装甲師団は、懸案であったVerkhnekumskyを陥落させるが、その前面には分厚いソ連軍の戦線が展開していた。
ソ連軍はアクセイ川南岸に進出していた部隊を、勝敗への影響が少ないことから撤収させた。ここで時間切れ終了となった。
この後の展開を想定するとムイシコワ川の渡河点を中心に川をはさんで両軍の殴り合いになるのは確か。遅滞戦術をとることでドイツ軍による邂逅エリアへの進出は阻止できそうだが、一方でここまでのソ連軍の出血もひどいため、戦線を張るだけの部隊ユニットを確保できずに戦線が崩れる可能性は最後まであるようにも思われる。また「戦闘カード」のイベントによる不測の事態が発生した場合もリスクとしてはあるだろう。
いずれにせよ両プレイヤーの一致した意見として、この後最後までうんざりするほどの殴り合いが続くことだけは確かだった。
ゲーム終了後、邂逅エリアとして「A」が指定されていたことが開示された。
1942年東部戦線の「冬の嵐」作戦を扱った作戦級ウォーゲーム『DONNERSCHLAG』(VUCA Simulations)を対戦。スターリングラードで包囲されたドイツ第6軍救出のため、マンシュタイン率いる装甲師団が厳冬のロシア平原を猛進する・・。上質なコンポーネント、(続)#ウォーゲーム #Wargames #ボードゲーム pic.twitter.com/rMsjj8UGFO
— yuishikani (@yuishikani1) 2025年4月15日
感想戦
 高いプレイアビリティが最大の特徴の作品です。ディベロップが行き届いており、マップやユニット、各種プレイエイドといったコンポーネントの質も優れています。難易度を抑えた取り組みやすいルールになっています。
高いプレイアビリティが最大の特徴の作品です。ディベロップが行き届いており、マップやユニット、各種プレイエイドといったコンポーネントの質も優れています。難易度を抑えた取り組みやすいルールになっています。
一方で、プレイアビリティ向上のために諸要素が簡略化され、部隊ユニットの性能も均質化されている点には注意が必要です。部隊名や部隊番号が単なる記号と化し、個々のユニットに思い入れを持つ余地がないため、ゲーム体験が平板に感じられることがあります。
カードマネジメントの面では、活性化カードは毎ターン使い切り、戦闘カードのみ1枚だけ次ターンに持ち越せるというシステムを採用しています。これにより意思決定の迷いが少なくなり、プレイアビリティは向上していますが、長期的な戦略を構築する余地は限られています。
ゲーム展開については、3つの邂逅エリアからゴール地点を選べるものの、そられは隣接しているため、結果的に一本道の進行になりがちです。渡河点の奪い合いなど局所的な戦術はあるものの、大局的な作戦要素は薄く、盤上のテクニックかコテ先勝負の色合いが強くなっています。
また、題材となった歴史的戦闘は明確ですが、ゲームの簡略化により歴史的事象を追体験している感覚が薄れ、純粋な戦闘ゲームに傾きすぎている印象も気になりました。
こうした特徴は同社の「ACROSS THE BUG RIVER」にも共通しており、開発の方向性が見て取れます。
総じて、取り組みやすく完成度の高い作品である一方、歴史シミュレーションとしての深みや個性を求めるプレイヤーには物足りなさを感じさせる可能性があります。プレイアビリティと歴史的リアリティのバランスをどう評価するかは、プレイヤーの好みによるところが大きいでしょう(ゲーム性とヒストリカル性のバランスは、初期のエポック社ゲームなどでも感じる感覚です)。
なおプレイの際はエラッタとかなりの補足が施された最新の英語ルールブックを参照することで、より円滑に進められるでしょう。
(終わり)